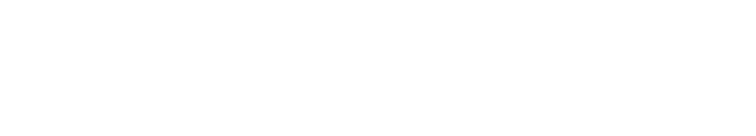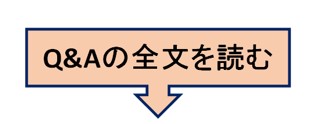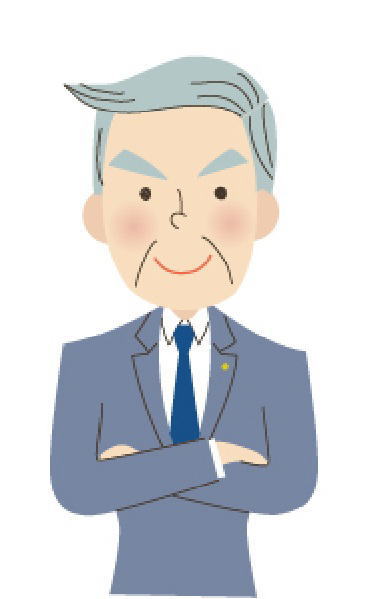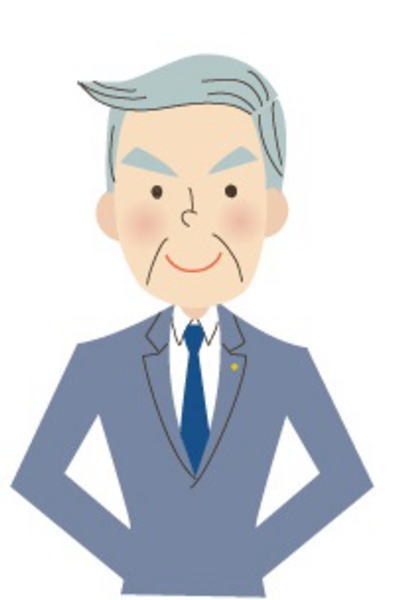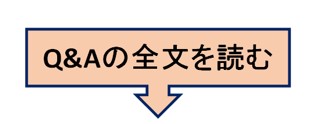
【題名】
認知症の母に借りたお金
【ご質問内容】
約11年前に母にお金をかりました。
その際に借用証書も作成しました。
6年ほど前から母が認知症になりました。
私は4人兄弟ですが、最近になり姉から返済の証拠(通帳履歴)と借りた金額が借用証書通りなのか確認したいと連絡がありました。
母の銀行の10年分履歴では返済は私の計算より20万少く、私の記憶では10年より前に20万は返していて、履歴にはのらなかったと考えています。
その場合は証拠がないため、その20万円は返済義務はありますが?
また借りた金額の証拠も振込があった通帳は処分していてできません。
姉は私が母からお金を借りていた事は10年前より知っていましたが、最近父が亡くなり認知症の母のお金の管理を始めるようになりました。それまでは私がしていました。
この借金の金額の確認をする術はありますか?当時の通帳は母も当方分もありません。また姉に証拠を見せる義務はありますか?
借金をした際に第三者の確認の必要性はあったのか?不備があったのか?
借金自体は借用証書の金額は今月返済予定ですが、そもそもの金額を疑われていて、証書も疑われています。
どうぞ宜しくお願い致します。
【ニックネーム】
弁天
【回答】
回答1.この借金の金額を確認する術はあるか?
借金全体の額を確認する方法は次のとおりです。
- 借用証書に記載された貸金額
- 金銭を受領したときに作成される領収書の記載額
- 口座で金銭が動いたのなら金融機関の取引履歴の取寄せ
で確認が可能です。
なお、借金に関して母と手紙やeメールでのやり取りで金額が記載されていれば、それらも借金の金額を確認する方法になります。
ただ、上記③については、履歴の開示期間が原則10年以内のため、通常の方法では取り寄せができないため、利用できません。
なお、回答3項に対応策を記載していますので、ご確認ください。
回答2:20万円の返済義務はあるか?
相談者が借金したことを認めた場合、借りた方相談者が弁済した事実を証明する必要があります。
相談者が20万円の弁済の証明ができなければ、支払義務があるということになります。
なお、借金した当時に分割払いの合意があった場合、10年以上前のある月の弁済分20万円につき消滅時効が主張できるのではないかという考え方もありえますが、債権としては分割額に債権が分断されるのではなく、まとめて1つの債権ですので、分割毎に別個の債権として時効消滅を主張することはむずかしいでしょう。
回答3:10年以上前の20万円弁済の証明方法は?
金融機関から取引履歴の取寄期間できるのは、原則として請求時点から約10年の範囲です。
そのため、問題となる20万円の弁済が10年以上前なら、履歴の取寄期間外になり、金融機関は履歴を送付してくれません。
但し、金融機関は最低でも20年間の記録は保存しています。
なぜなら、不法行為損害賠償請求権の請求できる期間は20年です。
そのため、金融機関としては、例えば行員が金銭を横領したと訴訟を提起されるような場合に備えて、最低でも20年間は記録を保存している必要がありますので、取引履歴や入出金伝票などは残しているはずです。
ただ、通常は出さないものどのように出させるのか、工夫が必要です。
例えば、照会対象期間を限定して、又、照会件数も減らして)かつなぜ取り寄せしないといけないのかという理由をがんばって記載して、《特別扱い》をしてもらうように依頼してみてはどうでしょうか。
金融機関が応じてくれるかはわかりませんが、試してみる価値はあるでしょう。
次に訴訟になった場合などは、訴訟の手続の中で、裁判所に調査嘱託や送付嘱託の申立てをして、裁判所から銀行に照会の書類を送付してもらう方法もありそうです。
そのような申し出があった場合、金融機関は《裁判所からだから》という理由で、特別扱いで資料を提出してくれる可能性もあると思います。
回答4:母が認知症、姉に証拠を見せる義務はあるのか?
貸金は母の権利です。
親子でも法的には人格が異なり他人ですので、当然に姉が貸金を請求する権利はなく、又、証拠を請求することもできません。
但し、母が姉に取り立てを委任しているような場合には、その委任により姉が貸金の返還を請求する権限を持つことになります。
なお、この場合でも姉の持つのは貸金の返還を請求する権利に過ぎず、それに対して相談者が証拠を示すか否かは自由です。
自らに有利な証拠を提出するのは義務ではなく、不利を免れるための防御方法でしかありません。
なお、母の認知症がひどくて意思能力のないような場合には、姉に対する委任行為自体が効力を有しませんので、姉からの請求は、関係のない他人からのものとして無視することができます。
回答5:借金をした際に第三者の確認の必要性はあったのか?
相談者の立場から言えば、借金をした場合に第三者の確認は不要です。
なぜなら、金銭を貸したことは母が証明することであり、第三者確認等の証拠を残しておくのは母のするべきことです。
次に、借金返済を証明するのは借りた側(相談者)ですので、相談者の方で証明する必要があります。
なお、貸金を弁済したかどうかを第三者という人での証明するのはできるだけ回避した方がいいでしょう。
証明は物(書類、例えば領収書や、送金証明など)など、形の残るものでする必要があります。
人は死にますし、嘘もつけば、記憶もあいまいになります。
人より物で証明できるようにする、これは証明の鉄則です。
(弁護士 大澤龍司)
![]()